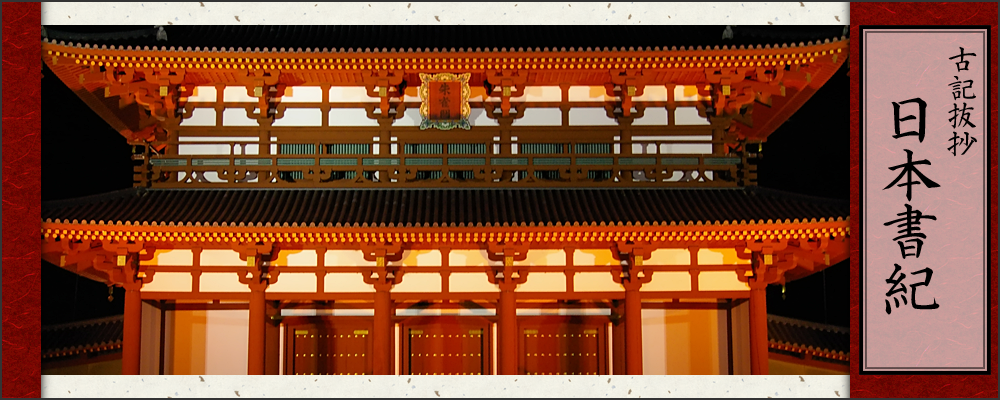
『日本書紀』
索部:古記抜抄:2013.03.13
・神代下 火中出産と竹の刀で臍の緒を切ること
・雄略紀 六年・七年 少子部栖軽のこと
・欽明紀 冒頭(秦大津父のこと)
・欽明紀十四年五月(樟木より仏像をつくらせる話)
・舒明紀九年(大きな星が流れ、僧旻が天狗であるという)
・推古紀七年四月(地震のこと)
・推古紀十一年春二月(来目皇子の薨去)
神代下 火中出産と竹の刀で臍の緒を切ること
(第三の一書)炎の中から火明命、火進命、火折彦火火出見尊が生まれ、すべてこの三柱の御子は火も害すことができなかった。母神もまた少しもけがをしなかった。ところで竹の刀でその生まれた子の臍緒を切ったのだが、その棄てた竹の刀がついに竹薮になった。それでその地を竹屋(たかや)というのである。また神吾田鹿葦津姫は卜定田(うらへだ)を作られたが、この田の名を狭名田(さなだ)といった。この田の稲で天甜酒(あめのたむさけ)を醸しておあがりになり、また渟浪田(ぬなた)の稲で御飯をたいておあがりになった。
このように、神吾田鹿葦津姫(かむあたかあしつひめ・木花咲耶姫)は有名な火中出産の際に、臍の緒を竹の刀で切った、という記述がある。第三の一書のみにあり、他の記述の中にはない。同様の話が『薩摩國風土記』からと思われる(異論もあるが)『塵袋』に引かれた逸文の中にもある。
ともかく、金属の刃物を用いずに竹に刃を付けてそれで臍の緒を切るという行為には、竹の持つ呪力に対する信仰があるものと見られ、南九州の一部では現代に入ってもこの手法がとられていたという(沖浦和光『竹の民俗誌』岩波新書)。同『竹の民俗誌』には、平末鎌初の『餓鬼草子』にも産婆が竹の篦で新生児の臍の緒を切っている様子が描かれていることが紹介されているが、その風習が先にあり、神話が後であるならば、広く「竹の刀で臍の緒は切るものだ」ということが行なわれていたかもしれない。
参考に『塵袋』の『薩摩國風土記逸文』とされる方は以下のようである。
(風土記に曰く)瓊瓊杵命が日向國の高茅穂に天降って、薩摩國閼駝郡の竹屋村の竹屋守の娘との間に二人の男子をもうけたさい、竹で刀をつくって臍の緒を切ったので、この地では今もそうする。
『日本書紀』と同じく「竹屋(たかや)」の地名由来を説く話になっているのだが、こういう。ここは今の鹿児島県南さつま市加世田内山田にある竹屋ヶ尾山という所が遺称地となるそうな。北に川下った方に「竹屋神社」もある。
▶「竹屋神社」(鹿児島県神社庁)
雄略紀 六年・七年 少子部栖軽のこと
(六年)三月、天皇は后妃に桑を摘ませ蚕を飼うことをお勧めになろうとし、栖軽に命じて、国内の蚕を集めさせた。そのとき、栖軽は誤って嬰児(わかご)を集めて天皇に奉った。天皇は笑って、嬰児を栖軽に賜り、おまえが養うようにと仰られた。こうして栖軽は少子部連の姓を賜った。
夏四月に、呉国が、使を遣わして貢献した。
七年秋七月、天皇は少子部栖軽に詔して、三諸岳(みもろのおか:三輪山)の神を見たいと思うから、力の勝っているおまえが捕えてくるようにと仰った。栖軽は三諸岳に登ると大蛇を捕えて、天皇にお見せした。天皇は斎戒なさらず(大蛇に対面したので)、大蛇は雷のような音をひびかせ、目を輝かせた。天皇はかしこまられて、目を覆ってご覧にならずに、殿中に隠れられた。天皇は大蛇を岳にお放ちになり、栖軽は雷(いかづち)と名を改め賜った。
※『日本書紀』の「すがる」は大変複雑な字を書くが(蜾に赢の貝が虫の字)、おそらく打てないので「栖軽」の表記とする。
話中の註釈として「この山(三諸岳)の神は大物主神というといわれ、ある説では、菟田の墨坂神であるともいう」と入る。墨坂神に関しては以下など参照。
▶「墨坂神社」(webサイト「玄松子の記憶」)
前段に栖軽が少子部連の姓を賜った由来が語られ、養蚕との関係があるらしいことが暗示されているが、どのような意味か詳しくは分からない。栖軽は神八井耳命を祖とするというから多氏と同じである。これらが後段の大蛇を捕まえる話と関係あるのかどうかも分からない。中段に「呉国が、使を遣わして貢献した。」と入るのが栖軽と関係あるのかどうかも、前段と後段が一連の話なのかどうかという点にかかるだろう。
ところでこの『日本書紀』の記述で重要なのは、栖軽が捕まえているのがあくまで大蛇だという点である。栖軽は雷神で蛇神の三輪山の神を捕まえた、とひとくくりで紹介されることが多いが、実は『霊異記』の類話と併せ見ないとそうはならないのだ。もちろん、「大蛇は雷のような音をひびかせ、目を輝かせた」と形容され、実際に栖軽は雷の名を賜っているのだから大蛇(大物主神か)と雷は連絡しているのだが、『日本書紀』が「雷を捕まえた話」なのかというと少しニュアンスが異なる、ということだ。
▶「雷を捉えし縁」(『霊異記』)
欽明紀 冒頭(秦大津父のこと)
天国排開広庭天皇(あめくにおしはらきひろにわのすめらみこと・欽明天皇)が幼少の頃、皇子の夢に人が出て来て秦大津父(はたのおおつち)という者を重用すれば壮年になって天下を治めることができるだろう、と言った。探すと本当に山城国紀郡の深草の里に秦大津父という人物がいたので、皇子は喜んで大津父に何か変わった事はなかったかと訊いた。大津父は伊勢に商いに行った際、山中に二匹の狼が咬みあって血まみれになっていたので、畏れ多い神(狼)に自重されますようというと争いをやめた事があるといった。皇子は(夢は)この報いに違いないと大津父を召し、手厚く遇した。大津父は大いに富を重ねて、皇子が皇位を継いで後は大蔵の司に任じられた。
秦氏というと雄略天皇の時代の秦酒公と聖徳太子を補佐したという秦河勝の名が良く知られるが、深草と名が出てくるとなると、この秦大津父が古い。秦氏と狐・狼(ジャッカル)の信仰の関係というのもあれこれ言われるが、その件でもこの話は重要だろう。
欽明紀十四年五月(樟木より仏像をつくらせる話)
夏五月一日(あるいは七日)、河内國から、泉郡茅渟(大阪湾)の海中から、仏教の楽の音がし、雷のように響き、日輪のように輝いているという報告があった。天皇が不思議に思い渡辺直を遣わし、海中を探らせると、照り輝く樟木があった。これを画工に命じて仏像二軀をつくらせた。これが吉野寺に光を放っている樟の像である。
『紀』における仏教の公伝はこの話の前年(欽明天皇十三年・552)のことである。これは物部・中臣が文句を言って、寺は焼かれて仏像は難波の堀江に流し捨てられるのだが、翌年には早くもこのように下ってたくさんの海で語られることになる海中の仏の話が出ているのだ。この仏像阿弥陀如来坐像・一名「放光樟像」は、『霊異記』『今昔』などにも語られ、今も奈良の世尊寺(吉野郡大淀町)に安置されている。
舒明紀九年(大きな星が流れ、僧旻が天狗であるという)
九年の春二月二十三日に、大きな星が東から西に流れ、雷のような音がした。人々は、流れ星の音だ、とか、地雷(つちのいかづち)だ、といったりしたが、僧旻は「流れ星ではない。これは天狗(あまつきつね)だ。天狗の吠える声が雷に似ているだけだ」と言った。
天狗(てんぐ)の話となるとまず紹介される天狗(あまつきつね)の話である。「日本書紀では流れ星を天狗と言っている」と簡単に書かれることも少なくないが、実際読むと分かるようにこれは少し注意が必要だ(間違いだ、というわけではないが)。
僧旻(みん・日文、推古天皇の時隋に渡り学んだ学問僧、後に国博士となる)は「流星ではない」と言っているのだ。他にも流星の記録は多いが、天狗であるという話があるのはここだけで、つまり、流星は流星と把握した上で、それとは違う怪異が起った、と言っているのだ。だから、飛鳥の人が流れ星を見て「天狗だ」と思っていたわけではない。そもそもこの話は隋唐でその故事を学んだ(『漢書』)僧旻がその知識を披露した、という程度のもので、前後の本邦における流星、また天狗(てんぐ)のイメージにはほとんど影響がないエピソードだと思う。
推古紀七年四月(地震のこと)
七年四月二十七日、地震がおきて建物すべてが倒壊した。それで全国に命じて地震(ない)の神を祀らせた。
推古天皇のころの規模とはいえ、一応国家プロジェクト(?)として地震の神を各地に祀ったというのは後にも先にもこのくらいだろう。このときの地震の神がいかなるものかはまったくわからない。
推古紀十一年春二月(来目皇子の薨去)
十一年春二月四日(新羅攻略の将軍であった)来目皇子が筑紫で薨去した。天皇は嘆き、大事に臨んで後を続けることができなくなったといわれた。周防国の佐波(防府市)に殯宮を設け、土師連猪手につかさどらせた。それで猪手連の子孫を、佐波(娑婆)連というようになったのである。のちに皇子は河内の埴生山に葬られた。
このように葬儀に関して「サバ」の名が古くに出ている。むろん周防の佐波は水にまつわる地名であり、それが先でその地の殯宮をつかさどった佐波(娑婆)連が後なのだが、古墳にかかわる氏族・土師氏が佐波の名を持っていたことは押さえておきたい。後、皇極天皇二年九月十一日に皇極天皇の母、吉備島皇祖母命(吉備姫王)が薨去され、十七日に土師娑婆連射手に喪儀を執り行うよう詔が出ている。
古記抜抄『日本書紀』





