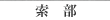山神社
索部:伊豆神社ノオト:2011.07.26
祭 神:大山祇命
創 建:元禄年間(伝・最古棟札延享年間)
例祭日:十月十五日
社 殿:権現造/南西向
住 所:伊東市池
伊豆伊東の大室山の南西側に池という集落があり、そこの鎮守がこの山神社さんである。今「池」はないが、かつてはトップの写真の田畑の部分が広大な湿地だったそうな。大雨のごとに水害にあい苦しんでいたが、安政の頃から水路の整備に着手し、明治三十四年に完成。今に見る田畑を得ることができた、と『神社誌』にある。
伊豆半島は海からすぐ山になる土地で、なだらかな土地というのがなく、大雨が降ればすぐに山雪崩・鉄砲水が問題となる。だからこの辺りの山村は決まって「山神社・水神社」のセットを祀ってきた、ということだ。この池の土地もすぐ近くに水神社の祠がある。
御社殿は熱海来宮神社さんから東伊豆町の水神社さんくらいまでの範囲の「標準社殿」とでもいうべきもので、鎮守格の神社にはこの社殿を採用しているところが頗る多い。そんなところも土地の特色と言えるだろうか。
所謂山村の鎮守さんで特筆するようなこともないのだが、このような鎮守さんは土地そのものの権化である。上の写真の御神紋を見ていただきたい。山の下に池があり、その下に稲の稔りを示すのだろう菊紋が入っている。まったく先のこの土地の歴史そのものと言える。
境内社は二社だが、写真右側が「阿夫利神社」であり、左奥が「子の神・第六天」となっている(社頭掲示)。『神社誌』では「第六天宮・鼠権現宮」となっている。ダイコクさん(子の神)を「鼠権現」と言っていたのですな。
「阿夫利神社」は相模大山阿夫利神社のことで、「池では毎年村の代表を送って参詣していた」とある。「阿夫利」とは「雨降り」の意であるとされ(相模大山は雨降り山とも呼ばれた)、周辺各地の農村からこの様に信仰を受けてきたのであります。あるいは伊豆に点在する「山神社」の多くは相模大山の分霊の側面があるのかもしれない。
「第六天」は関東一帯で地神としてたくさん祀られてきたものの流れだろうが、ここでは「快楽を司り、夫婦和合、縁結びの神として信仰されてきた」というように道祖神さん等に近いものとなっていたようだ。珍しいものではなく、東伊豆も伊東から河津にかけて第六天(もと第六天)は点在している。
参拝記
山神社へは平成二十二年の八月二十八日に参拝している。伊東線南伊東駅で降りて、ひたすら歩いて伊豆高原の先、赤沢まで行った。八月終りの炎天下であり、思えば今までで一番「危険」な神社巡りだった。伊豆高原駅近くの八幡宮来宮神社から赤沢へ向う途中でへたり込んだ記憶がある(笑)。
そのようであったので、山神社さんのこの涼しげな社叢が目に入ったときはまず「助かった……」と思ったものだ。神社の社叢が日陰を提供してくれるものだという感覚はここで身に染みたといって良い。
さて、この山神社さんの池の土地。ここは再訪の可能性もあるところだ。大室山と修験・引手力男神社と修験・疣とり伝説などが未解消のまま課題となっている。天城連峰のお膝元であることもあり、内地と海側の文化の連なりを考える上で、この辺りから南伊東の八幡宮来宮神社の方は大変重要なところなのだ(その割に目立った話がない)。資料上追えるものを追った後に、またご挨拶に伺うことになるだろう。
山神社(伊東市池) 2011.07.26